- INTERVIEW
農業界を変えたい -新しい農業の形と"ゆめの大地"の関係

Interviewee
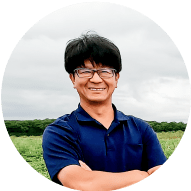
五十嵐 重明
IGARASHI Shigeaki
株式会社けーあいファーム 代表
北海道釧路市出身。
東京での10年間の会社員生活ののち、2004年札幌で会社員をしながら千歳市にて農業を始める。その後4年間の兼業農家を経て、農業専業になる。
2013年株式会社けーあいファームを創立。
圃場のすぐ上空を飛行機が通り過ぎていく。
新千歳空港からほど近い場所に広大な畑を有する「けーあいファーム」。
けーあいファームに私たちがお邪魔したのは、ちょうど今シーズン第1回目のじゃがいも収穫の日。
今年からドイツ製の大型機械を導入し、この日が初めての運転だったそう。太陽の光でピカピカに光る真っ赤なボディが畑を一直線に進んでいき、その上では何人ものスタッフがじゃがいもを選別していく。一度に収穫できる量はなんと6トン。収穫したじゃがいもを機械からコンテナに移し替える際、人の背丈ほどもある箱がいくつも満杯になっていく様子は圧巻だった。
けーあいファームは、数年前から「ゆめの大地」を生産する株式会社北海道中央牧場と連携し、養豚事業を開始。耕畜連携による循環型農業に取り組むとともに、収穫機やドローンといった最新の機器を適宜導入するなど、スマート農業*1を含む先端農業の先陣を切っている。
しかし、当の五十嵐社長は「そもそも、スマート農業*1が何か、実はあまりよくわかっていない」と言う。「ドローンも、スマート農業*1をやるために始めたわけではなく、やるべきだと思ってやったらなんとスマート農業*1でした、というような感じです」。
時代を先取りする農業に取り組みつつ、その実、それを狙っているわけではない。
必要だから導入する。非常にシンプルでありながら、それこそが正しい形なのかもしれない。
※1 ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進している新たな農業のこと。
会社員から二足の草鞋、
そして「農家」へ

五十嵐社長は東京での会社員時代を経て、北海道に戻って兼業農家、そして専業農家へ移行したという珍しい経歴を持つ。
きっかけは彼の妻の実家にあった小さな畑だったという。「東京にいてほぼほぼアスファルトしか見ないような生活を送っていて、そして僕は生まれが釧路なので、畑が無いんです。なので、ちっちゃい家庭菜園くらいの土地が、広大な土地に見えたんですよ」
五十嵐社長は空き地になっていたその土地で野菜を作り始め、販売にも着手。こうした“家庭菜園”の延長線上で少しずつ規模を拡大していった結果、ある時にふと「俺、農家みたいだな」と気づいたのだとか。
いつの間にか……というところから始まった農業だったが、今は“日本の食を守る”という意識を強く抱いており、それは日本一レベルの規模を持つ一因にもなっている。「家庭菜園の延長から始めたのが責任のあることなんだなと思うようになって。それなりのものを作ってそれなりの量を作って、それなりの供給をしきゃならないんだ、ということを後から思って、この規模になっていきました」
Point
雇用について
五十嵐社長の会社員経験が活かされた仕組みとして、一般企業のような雇用制度が整備されているという点があります。休日を十分に与えたり社会保険を導入したりなど、「きちんとした会社にする」という目標は最初から抱いていたのだそう。最初は同業者から「そんな考えで農業をやっていては務まらないよ」と忠告を受けることもありましたが、現在はスタッフも育っていき、有給も全て消化。こういった側面からも、今の時代に即した農業の形を提示していると言えるでしょう。
スマート農業で
誰もが熟練者に
冒頭でも触れたとおり、五十嵐社長はスマート農業をやろうとして始めたわけではなかった。ではなぜ最新の機械やGPSを利用した自動運転、自動操縦の機械を導入していったのかというと、“熟練度に関わらず誰でも作業ができる環境を作りたかったから”だという。
「弊社は、豚肉については業界内で後発にあたりますが、品種による差別化や餌の研究など、ブランド牛で培った独自のノウ・ハウを下地に、妥協無く追及しています。」
また、北海道の気候によるところも大きいと五十嵐社長は語る。「北海道って植えられる期間が短いんですよね。一気に植えちゃうと一気に掘らなきゃいけないんで。そうすると小型の機械で掘っていたら間に合わなくなってしまう。だからどうしても大型の機械が必要なんです」
ただしどんな作物でも機械を使っているわけではない。例えばかぼちゃは収穫期になると毎日40人が畑に出向くという。一気にとらなければならないものは機械で、そうでないものは人の手で。現状に合ったやり方を模索しながら、“スマート農業”と日々向き合っている。
Side story

JGAP認証
けーあいファームでは2009年にエコファーマー認証を、そして2015年にJGAP認証を取得しています。この2つはどちらも持続可能な農業に取り組んでいる農業者に与えられる印ですが、取得にあたっては“会社の改善”という意図もあったのだそう。第三者による定期的なチェックによって「やらなきゃ」という積極的機運が社内全体に広がり、五十嵐社長が言わずともルールが勝手にできていくなど常に良い環境が整っていきました。会社が良くなればスタッフも働きやすくなり、そして生産される作物もより安心・安全になる。そんな素敵な流れが育まれています。
北海道農政部「エコファーマー認定について」 日本GAP協会
「JGAP認証について」
ブランド豚”ゆめの大地”が
野菜を育む

ブランド豚“ゆめの大地”を生産する株式会社北海道中央牧場との関係は7年ほど前から。最初は中央牧場で作られた豚糞由来の堆肥を畑で使用するのみだったが、令和2年からは平取町に「くれないファーム」を設立。中央牧場から生後約75日の仔豚を受け入れ、約110日肥育。そして株式会社日高食肉センターへ出荷するという流れが構築された。
養豚を始めたことで、自社内での循環型農業にも力を入れるように。そもそも堆肥は農業界にも賛否両論あり、入れる量に関しても様々な意見が飛び交っているのだとか。しかし五十嵐社長は「養豚に取り組む以上、否応なしにできる堆肥をいかにして上手く利用できるか」という方向に舵を切った。
「堆肥が過剰に入っていかなければならない環境のなかで、どうやったらいいのか。それに合う作物があるのかないのか」を模索し、大量に漉き込まれた土と相性が良い野菜を先に植え、その後で別のを……という具合に調整をしながら野菜を作っている。さらに、ただ豚糞を堆肥化するだけでなく、カルシウムを配合するなど質向上への研究にも取り組んでいるそうだ。
化学肥料に頼ることのリスク

こういった堆肥の活用は、“化学肥料に頼らない”という思いとも関係している。日本の食料自給率はカロリーベースで約38%(令和元年度)だが、実は種や肥料自体はほとんど輸入に頼っており、真の自給率は8%とも言われている。
そんななか、実は昨年、中国からの輸入減少やロシアのウクライナ侵攻などにより、肥料の供給は非常に危機的な状況にあった。けーあいファームも例外ではなく、いつも利用していた店から「1個も無いです」と突然言われたという。
そのときは他施設の在庫や他国からの輸入開始で窮地を逃れたが、現在も価格は高騰したまま。安くなる兆しもなく、現在の輸入が止まってしまう可能性もゼロではない。「だからやっぱり、堆肥や循環型農業といったことを今からやっていかないと、もうだめなんだなってとこに今きているんです」。そう話す五十嵐社長の表情も、事態の深刻さを物語っていた。
耕畜連携の推進、そして
「なりたい職業1位」を目指して

今後はさらに耕畜連携を推し進めていきたいと五十嵐社長は語る。「自分のところで肥料や餌を作れると良いですよね。それには課題がありすぎて、そう簡単にやろうということにはならないですけど。国内で自給するのは100%無理だとしても、ある程度は作ってかなきゃいけないなとは思います」。昨年、肥料の枯渇という危機的状況に見舞われたからこそ、その言葉には確かな重みがあった。
そしてこの取り組みは、もちろん環境への配慮でもある。「化学物質でものを作るよりはずっといいですし、環境的なことを重視してやりたいなということです」。
一方、“農業”に対するイメージを変えていきたいという思いも。
けーあいファームは経営システムから規模感、そして作業方法に至るまで、従来の農業とは一線を画す。何十年農家を生業にしてきた人ですら乗る機会が滅多にない大型機械を、昨年入社したばかりの従業員が乗れるような環境がここにはあるのだ。「そこにモチベーションを持ってもらって、『自分の職業カッコいいな』って思うような仕事にしたい」と語る。
「いつか小学生・中学生に聞いたなりたい職業1位になればなっていうのは、ちょっと思いますね」。微笑みながら最後にこう話してくれた五十嵐社長。穏やかな表情のなかに、この大きな農場と多くの従業員を束ねる力強さを感じた。
Editor

三谷 乃亜
MITANI Noa
エッセイスト
生まれも育ちも北海道。食べることが好きで、スイーツ・パン・かぼちゃには目がない。特にかぼちゃへの想いが強く、シーズン中は飽きられないような調理法を模索しつつ、山吹色を食卓にねじ込み続けている。
北海道デジタル絵本コンテストにて、優秀賞(第1回)と特別賞(第2回)を受賞(共に作話担当)。












